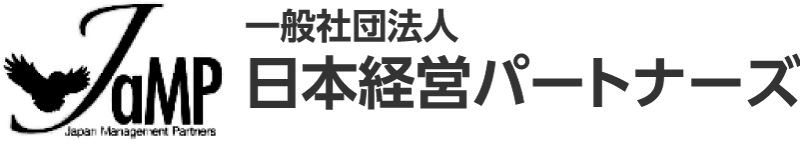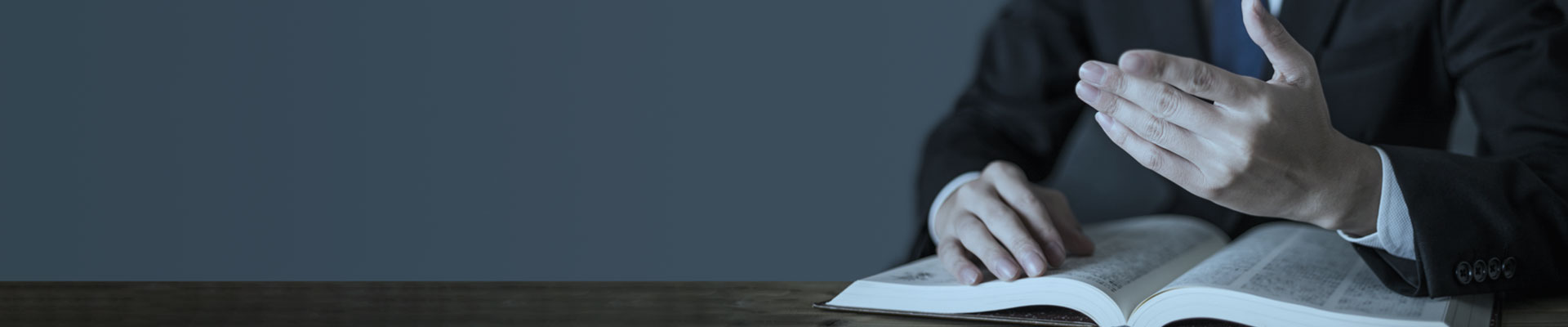
PROVERB
経営に役立つ格言
偉大な先人たちが残した格言には
経営に役立つ思想や哲学が詰まっています。
日本経営パートナーズではその中でも
3つの格言にスポットを当てご紹介いたします。
きっと現状の課題を打開するための
きっかけになることでしょう。
打つ手は無限

経営のスタイルは100社あれば100通り、一つとして同じ会社はありません。
今の経営と未来の経営、どちらに重きを置くかでもやり方は変わります。
経営には決まった形はなく、経営者が信じた道を切り開く、それが経営です。
主なテーマごとに、経営の「打つ手」を考えてみます。
①売上を伸ばして会社を大きくしたい
トップ自らが営業が得意な会社は、経理や総務などの銃後の守りを固めるべし!
技術は得意でも営業が苦手な会社は、営業が得意な会社と組むべし!
自社で限界があるならM&Aや事業提携で他人の力を利用すべし!
②人材が足りない
今いる人材を徹底的に教育することを一番最初に行うべし!
人材不足を嘆く前に、小さくても人が集まる魅力的な会社にすることを行うべし!
人を動かす力がある経営者は、もっとも有能な経営者である!
③キャッシュをまわす
キャッシュは人間の血液と同じ、まわすためには健康な会社でなければならない!
お客さまとはWIN-WINの関係であるべし!三方良しは究極のビジネススタイル!
銀行はパートナー、経営者の夢を信じてキャッシュを提供する!
経営のやり方やピンチを切り抜ける方法も無限にあります。
「打つ手は無限」数多くの会社の経営を見て、痛切に感じる経営の鉄則です。
どんな時も、いつの時代でも、あきらめない限り、必ず道は開けます。
天の時・地の利・人の和

中国の孟子が残した戦国時代の言葉の一つです。
「天候による好機も土地の有利な条件には及ばず、
土地の有利な条件も人の強いつながりには及ばない」という教えです。
経営において、とても興味深い言葉で、
チャンスをものにするには立地や資金、ライバルとのポジションで勝ることと、
社内・社外の人との目標設定が明確になっていることが大切であるということです。
<決断の時>
”決断”は社長業で最も大切なことです。
新たな事業を行うとき
投資をするとき
人を判断するとき
撤退をするとき
すべての「とき」はこの”決断”につながります。
その時にこの「天の時・地の利・人の和」」が揃っているかよく見極めてください。
あえて、つけ加えると、”決断”をしたら、一晩寝て、翌朝、もう一度”よし!”と思ったら大丈夫です。
一度の決断で決めるより、一晩間をおいて二度目の決断で実行する。
成功の秘訣は、”決断”であり、あとは一歩を踏み出すだけです。
計画はち密に、行動は大胆に

臆病な経営者と大胆な経営者、どちらでしょうか。
臆病すぎるとチャンスを逃し!大胆すぎると足元をすくわれる!
経営を行うには、このどちらも大切です。
経営者は人生という限られた時間の中で、大きな変化に立ち向かっています。
臆病すぎて”決断”を先延ばしにすると、時間だけが過ぎてしまい、タイミングを逃します。
一方、大胆すぎると思わぬ計算違いや相手からの誤解を招き、事業が立ち行かなくことがあります。
経営者としての経験から言うと、矛盾しているように聞こえますがこのように考えます。
臆病すぎるくらいがちょうどいい しかし、大胆になれない経営者は成功しない
10年後を正確に見通すことができる人間はいません。
もっと大きな社会の変化、人の価値観の変化、世界情勢の変化、環境の変化など、変化だらけです。
結果、「予測は未定」「やってみなければわからない」なかで経営を行っています。
だからといって、なんでもOKではありません。今集められる情報はとことん集める、昔のことを教訓にする。
計画はできる限り秘密に立てる、リスクはなんだ!右がダメなら左はあるか!最大損失で会社は耐えれるか!
さあ、考えて、考えて、計画を立てたら行動は大胆に実行しよう!
経営は足し算ではありません、一本道ではありません、常に変化をしながら進めるものです。
計画段階で、「一の矢」「二の矢」「三の矢」まで考えておけば、成功確率は99.9%です。
緻密な計画に裏打ちされた大胆な行動は「運」をも味方にできるはずです。
機先を制する
相手が事を行なう直前に行動を起こし、相手の計画、気勢を抑える。
急いては事を仕損じる
物事は慌てて行うと、かえって失敗することが多い。急ぐときほど、冷静沈着に行動せよという教訓。
攻撃は最大の防御なり
絶えず攻撃し相手の攻撃の余裕を奪うのが結果的に最良の護身だということ。
防御なくして攻撃なし
攻撃力ばかり高くても簡単に相手に得点を許すようでは負けてしまうという意味です。
思い立ったが吉日
何かしようと決意したら、そう思った日を吉日としてすぐ取りかかるのが良いという意味。思い立つ日が吉日、思い立ったら吉日とも。この場合、「吉日」は物事をするのに良い日を意味する。
郷に入っては郷に従え
その土地(又は社会集団一般)に入ったら、自分の価値観と異なっていても、その土地(集団)の慣習や風俗にあった行動をとるべきである。
将を射んとすれば先ず馬を射よ
他人を自分の考えに従わせようとするなら、まずその人が最も信頼している人物を従わせるのが、成功の早道であることのたとえ。
人事を尽くして天命を待つ
人間の能力で可能な限りの努力をしたら、あとは焦らず静かに結果を天の意思に任せる、という意味があります。
全力を尽くしたのであれば事の成否は人知を越えた天任せなのだから、「どんな結果になろうとも後悔はない」という心境を表す言葉としても使用されます。
船頭多くして船山に上る
指図する人が多過ぎるとかえって統率がとれず意に反した方向に物事が進んで行くことの意。
損して得取れ
損して得取れとは、目先の利益や損失ばかりにとらわれてしまってはいけないといましめることわざです。一時は損をしたとしても、最終的には大きな利益を得られるように、物事を長期的な視点で見ることが大事だという意味を持ちます。
泣いて馬謖を斬る
《中国の三国時代、蜀(しょく)の諸葛孔明(しょかつこうめい)は日ごろ重用していた臣下の馬謖が命に従わず魏に大敗したために、泣いて斬罪に処したという「蜀志」馬謖伝の故事から》規律を保つためには、たとえ愛する者であっても、違反者は厳しく処分することのたとえ。
人間いたるところに青山あり
人間はどこにでも骨を埋める場所ぐらいはあるということで、故郷ばかりが墓所ではないことをいう。人間は大志を抱き、故郷を出て大いに活躍せよという教訓。
案ずるより産むが易し
実際に行ってみると、事前に心配していたほど難しくはないということです。由来は、言葉の通り妊婦さんが、赤ちゃんを産むのに不安になっていても実際産んでみたらそれほどのことでもなかったということから来ています。
好いたことはせぬが損
好きなことをしないのは損だということ。 やりたいことがあれば、あとで悔やまないようにやったほうがよい。
鉄は熱いうちに打て
物事は時期を逃さないように、関心や情熱があるうちに事を運ばないと成功しにくくなる。という意味。
浮き沈み七度(ななたび)
うきしずみななたび人生は、好調のときもあれば不調のときもある。浮沈盛衰のくり返しこそが、人生だといえるというたとえ。
愚公山を移す
どんなに困難なことでも努力を続ければ、やがては成就するというたとえ。
石の上にも三年
冷たい石の上でも3年も座りつづけていれば暖まってくる。がまん強く辛抱すれば必ず成功することのたとえ。