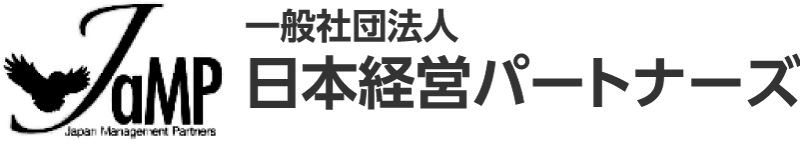Q&A
よくある質問
日本経営パートナーズに関する
よくある質問をご紹介します。
ABOUT US
日本経営パートナーズについて
一般社団法人 日本経営パートナーズとはどんな会社ですか?
地域に役立つ“社長の知恵袋”を経営理念とし、経営改善に取り組む中小企業診断士、事業再生を行う認定事業再生士、労務改善を行う社会保険労務士、財務改善を行う公認会計士などの専門家の集団です。
元上場企業の役員経験者や民事再生の経験者など、多士済々のメンバーがサポートできる体制で取組みを行っています。
どのようなコンサルティングをやっていますか?
お客様の要望によってチームでの取り組みを特徴としています。認定支援機関としての経営改善計画の策定、事業再生計画の策定などや、売上アップのための営業マン教育、工場コストの削減、資金繰り改善のための取組みや銀行との交渉など、実務に沿った取組みを行います。
経営コンサルタントを使うメリットは何ですか?
【費用的なメリット】
経営コンサルタントは、経営を外部からの客観的な視点で見直しを行います。社長の悩みや経営の課題を共有しながら、専門家としてアドバイスするとともに、必要に応じて社員教育やプロジェクトの推進などを行います。外部の専門家として、かかる費用以上の改善効果の実現のための取り組みを行います。
【社長にとってのメリット】
経営者の方々は、日々いろいろな問題に対処が迫られ悩まれていることが多いと思います。私たち経営コンサルタントは“社長の知恵袋”として、よき相談相手となるべき存在です。秘密保持契約のもと、信頼できる経営パートナーとしてお役に立てると思います。
費用はいくらくらいかかりますか?
コンサルティングの内容によって費用は異なります。経営改善計画の策定や事業計画の策定の場合は補助金の活用も検討します。
また、継続的な改善の場合は顧問契約という形態もあり、月額10万円~20万円程度となっています。お気軽に相談いただければ、改善効果以上の費用負担にならないようご期待にそえるものにします。
RECONSTRUCTION AND REVITALIZATION
企業の再建・事業再生について
事業再生とはどのような方法がありますか ?
事業再生といっても、その方法は多岐にわたります。一般的には、自力再生 (自らの経営を見直すことで再生を実現する)以外に、金融機関の協力を得ながら行うリスケ(弁済計画の猶予)・有利子負債の削減、不採算部門の見直し(不採算部門の切り離しやスポンサー探しなど)、M&Aなどによる事業売却などの方法があります。また、法的手続きによる民事再生手続きや特別清算など、さまざまな手法を組み合わせて一日も早い事業の再生を実現します。
過去の過大負債や遊休資産などはどのようにしますか?
過大負債の解決は、BS改善や銀行交渉などについて経営者の方と、具体的な解決方法について打合せを行いながら方策の決定を行います。また、遊休資産については提携する不動産会社や建設会社の協力のもと、秘密保持契約を締結しながら最も効果的な活用または売却についての方策を検討します。
会社の借り入れに対する経営者保証はどこまで責任がありますか?
会社の借り入れに対して債務処理が行われても、不足があれば経営者保証が求められます。この場合、個人資産で負債が処理できなければ破産手続きを行わなければならないことも多くあります。しかしながら、平成26年に「経営者保証に関するガイドライン」が出されており、債権者との協議によって保証の範囲についても見直しの可能性があります。安易に破産に持ち込むことなく、粘り強く交渉をしていく必要があります。
事業承継で気をつけることはありますか?
企業は取引先、ブランドや従業員など多くのかかわりを持って事業を行っています。事業承継は、このような関係する人に対する責任とともに、社長本人のハッピーリタイアを設計するための計画づくりです。
後継者が社内ではっきりしている場合には、「いつ」「どのような方法で」経営者交代を行うのか、そのための株式の譲渡はどのように行うのかを経営者教育も含めて明確にしなくてはいけません。また、後継者がいない場合には、外部から連れてくるのか、 従業員への承継なども視野に入れる必要があります。さらに、M&Aによる事業の売却などの方法もあります。事業承継は、経営者の事業の集大成であるといます。時間をかけて、それぞれの手法について十分な検討を行うことが事業承継を上手に行う第一ステップとなります。
事業承継計画はどのように立てたらいいのですか?
計画の立案にあたっては、最初に会社を取り巻く状況を正確に把握することが大切です。
具体的には、
①会社の現状(PL,BS,将来の計画や従業員の状況)、
②会社の経営リスク(負債、経営者の交代が事業に与える影響)、
③経営者自身の状況(自社株式の保有状況、個人名義の資産、個人の負債や経営者保証)、
④後継者の状況 (年齢や経営能力、社内での人望、経営意欲)、
⑤相続発生時の予想(相続税額、納税方法、納税資金)、
などについての検討が必要です。
一つひとつ、計画の書面に落としながら考える時間を持つことが、事業承継をスムーズに行うためには必要です。
後継者の教育はどのようにしたらよいのか?
後継者は、社長から見たらどこまで行っても頼りなく見えることでしょう。このような場合、事業承継計画をつくって、社長と後継者が一緒になってそのスケジュールと引継ぎ方法を検討することを勧めています。実行にあたっては、プロジェクト方式により、時期を明確にしながら、そこれまでに解決すべき課題 (株式、退職金、役割等)について共通の認識が持てるように進めていくのが最善の方法になります。
外部の経営コンサルタントは、その課題ごとに社長の想いを後継者の方に理解をしてもらうためのアドバイスを行います。
ABOUT M&A
M&Aについて
M&Aは中小企業でもできますか?
M&Aというと大企業が行うものと思いがちですが、中小企業でも活用することができます。事業承継のための方法としても、経営者がハッピーリタイアをするための方法としても有効です。M&Aは、従業員や取引先に不安を与えないようにできるだけ秘密裏に進める必要があります。また、大手のコンサルティング会社では費用が高いところもありますので、コンサルティング会社の選定にあたっては内容をよく確認して、売却費用と手数料をしっかりと確認をしたうえで信頼できる会社を選んでください。
M&Aにはどのような方法がありますか?
会社の全部を譲渡する場合には、株式の売却、株式交換、合併などの方法があります。この場合には、株式の評価を行なったうえでその対価を現金または相手先の株式で受取ります。会社の一部を売却する場合には、会社分割、事業の一部譲渡の方式をとります。この場合には、事業価値を算定してその対価を現金等で受取ります。いずれの場合にも、従業員の雇用の継続や取引先の継続を前提に交渉を行うこととなります。
M&Aの手順はどのように行いますか?
手順としては
仲介機関(アドバイザー)の選定
↓
売却候補企業への打診(ノンネームシート)
↓
秘密保持契約の締結条件交渉
↓
基本合意書の締結
↓
トップ面談
↓
デューデリジェンス(DD)
↓
詳細調査
↓
売買契約書の締結
↓
クロージング(資金決済)
という流れが一般的です。
内容によって、手順が多少は前後しますが、大切なことは仲介機関 (アドバイザー) が信頼できることと、相手先企業にとって魅力のある会社であることです。